既 刊
表象交通論/現代思想/ 文化人類学・民族学・民俗学・歴史人類学/ 美術造形・美術史
●プリミティヴアート
★ 第47回日本翻訳出版文化賞受賞 ★
フランツ・ボアズ【著】/大村敬一【訳】 ISBN: 978-4-86209-035-5 C3039 [A5判上製]664p 21cm (2011-02-26出版) 定価=本体8500円+税
§「芸術人類学」ボアズ名著、初の完訳。
「プリミティヴィズムはわれわれの後ろにあるのではなく われわれの前にある」(レヴィ=ストロース) ◎アメリカ人類学の父◎「構造人類学の先駆者」として、モースやレヴィ=ストロースらに深く影響を及ぼしたボアズ 、1927年初版、待望の完訳。
【目次】 緒言― プリミティヴな人々の心的態度・文化と歴史的な発達、芸術の発達にかかわる動的条件の研究 1.序論― 芸術とは何か? 芸術における技法の熟達、芸術なるものの内容が感情に訴えかける魅力 2.芸術の形式的要素― 均斉のとれたかたちと妙技、技巧が欠けている場合の芸術的なかたち、平面、目立った線、均斉のとれた曲線、シンメトリー、逆シンメトリー、リズム、縁のデザイン、突き出たところへの装飾 3.具象芸術― 表現と具象芸術、プリミティヴな象徴表現と写実表現、表象の様式に技法がおよぼす影響 4.象徴的意味― 象徴的な解釈の広範な分布、象徴に一貫性がない場合、デザインの名称、様式化に関する諸研究、よく似たデザインに対するさまざまな説明の地理的分布、意味の読み込み、具象的な傾向に従って幾何学的なかたちが発達する場合、解釈の不安定性に対する行為のパターンの安定性、装飾の紋地がもつ効果、象徴的な表現の方法が及ぼす効果 5.様式― 様式の問題、身体運動の習慣とかたち、かたちの凝縮、新たな素材へのかたちの転移、技法によって決まるかたち、様式の個性、文化的な背景の中でのつくり手、様式が発明におよぼす影響、様式における形式的な要素、芸術形式の拡がりとその地域的な発達、同じ部族や社会における様式の多様性 6.北アメリカ北部太平洋沿岸の芸術― 動物のかたちの象徴的な表現、象徴の概要、副次的な象徴は規範に厳密に従うわけではない、オオカミ―同じ動物がさまざまなかたちで表される場合、さまざまな解釈、断片的な象徴の活用、動物のかたちを装飾の紋地に合わせて調整する、動物の表象における形式的な要素、チルカット・ブランケットにおけるデザインの配置、箱におけるデザインの配置、食べ物の盛り皿デザインの配置、幾何学的な要素、ジョージア湾の古い芸術様式、写実的な表現、籠細工における幾何学的なデザイン 7.プリミティヴな言語芸術と音楽とダンス― 文芸と音楽とダンスの普遍的な発生、歌と音楽とダンスの関係、プリミティヴな散文、リズム、強調、シンメトリー、メタファー、詩的な描写、文芸の形式に反映された地域の文化、物語の象徴的な意味、同じ部族にさまざまな文芸の様式が見てとれる場合 結論

【著者紹介】 フランツ・ボアズ(1858~1942年) ドイツのヴェストファーレン州ミンデンにユダヤ系ドイツ人として生まれる。ハイデルベルグ大学、ボン大学、キール大学で物理学と生物学を学び、1881年、物理学の博士号を取得。物理学で博士学位論文を書き終えた後、物理学から地理学に転向、1882年、カナダ極北圏で地理学的な研究を実施する準備を行うためベルリンに向かった。当時、学会の中心にいた医学者ルドルフ・ウィルヒョウ、民族学者アドルフ・バスチアンらの知遇をえて、1883年8月から翌年8月の間、カナダ東部極北圏バフィン島のイヌイトの間ではじめてのフィールドワークを実施、続いて1885年にはカナダ、ブリティッシュ・コロンビア州でのはじめての調査に赴く。1887年にアメリカに移住するまで、ベルリン王立民族学博物館でバスチアンの助手を務め、アドリアン・ヤコブセンがカナダのブリティッシュ・コロンビアで収集した北西海岸インディアンの資料の整理にたずさわった。 1887年、婚約者のマリー・クラコヴァイザーと結婚、渡米して、科学雑誌『サイエンス』の記者、1888年にはクラーク大学形質人類学の講師の職をえて、アメリカ合衆国に永住することを決意した。1888年から8年間にわたって計5回、延べ約1年間、イギリス学術振興連盟からの資金を得て、ブリティッシュ・コロンビア州で北西海岸インディアンの調査を実施。1899年、コロンビア大学人類学教授に就任。並行してアメリカ自然史博物館でも働き、1892年から1902年まで、ロシアからアメリカ、カナダにわたる北太平洋沿岸部の人類学研究の基礎となった伝説的な大規模広域調査、ジェサップ北太平洋調査(2)の指揮をとり、1901年から1905年まで同博物館の館長もつとめた。コロンビア大学を1937年に退官するまで、ボアズはアメリカの近代人類学を主導する人類学者を次々に育てていった。アルフレッド・クローバー、ルース・ベネディクト、マーガレット・ミード、ポール・ラディン、マーヴィル・ハースコヴィッツ、ロバート・ローウィー、言語人類学者のエドワード・サピアなど、20世紀前半のアメリカ人類学を代表する人類学者がボアズのもとで育っている。 生涯にわたって書いた論文は600本にもわたり、1万ページ以上と言われる北西海岸先住民の民族誌をはじめ、本書『プリミティヴ アート』(Boas 1927)、『未開人の心性』(Boas 1911b)、『人類学と近代の生活』(Boas 1928)、論文集『人種・言語・文化』(Boas 1940)などの著書を残している。また、学会のオーガナイザーとしても活躍、1888年にはアメリカ民俗学会を創設、1900年にはアメリカ民族学会を復興、1902年にアメリカの人類学者の全国組織・アメリカ人類学会の創設にもかかわった。1942年12月、84歳で死去。
【訳者紹介】 大村敬一(1966年~) 湘南生まれ。1997年3月、早稲田大学・大学院文学研究科・考古学専攻・博士後期課程、満期修了。博士(文学)。現在、大阪大学・大学院言語文化研究科・准教授。専門は人類学。カナダ極北圏のイヌイトとカナダ北西海岸インディアンを主たる調査地としている。 共編著に、Self and Other Images of Hunter-Gatherers (Senri Ethnological Studies No. 60), Henry Stewart, Alan Barnard and Keiichi Omura (eds.), Osaka: National Museum of Ethnology, 2002. 『文化人類学研究:先住民の世界』(本多俊和・葛野浩昭・大村敬一編、東京:放送大学教育振興会、2005年)。『極北と森林の記憶:イヌイットと北西海岸インディアンのアート』(齋藤玲子・岸上伸啓・大村敬一編、京都:昭和堂、2009年)。『グローバリゼーションの人類学:争いと和解の諸相』(本多俊和・大村敬一編、東京:放送大学教育振興会、2011年)がある。
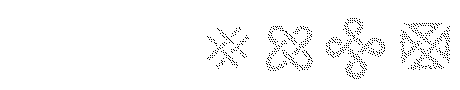
【書評】
今福龍太氏(東京外語大学教授)/読売新聞 2011.5.15朝刊
20世紀の学問界のなかでも、恐らくもっとも影響力ある巨人的知性の一人であったボアズの芸術人類学をめぐる主著が、ついに日本語になった。原著刊行はアメリカ人類学の曙の時代である1927年。遥かに遠い時間をわたって、しかし不思議にアクチュアルな気配とともに、この大著の完訳が現れたことを歓迎したい。
プリミティヴな部族芸術をめぐる精緻な観察と理論に裏打ちされた魅力的な総覧である。体系的な記述のなかで、造形芸術の形式を決定する技芸の洗練、芸術における写実と象徴の関係、様式のなかの個性と多様性の問題、プリミティヴな歌や音楽やダンスの統合的な存在様態などが、全世界からの素材を援用しながら子細に論じられる。とりわけボアズ自身のフィールドである北アメリカ北部太平洋岸の諸部族の物質文化・芸術に関する分析が白眉だ。三百枚を超える図版は、トーテムポールから仮面、籠、毛布、刺繍、儀礼的祭具にいたるまで、民族学的な文脈を明確に提示しつつ、デザイン的にも美しく援用されていてそれだけでも飽きさせない。
ボアズは「パパ・フランツ」と呼ばれ、厳格かつ寛大な学問的父として多くのアメリカの指導的人類学者を育てた。『菊と刀』や『文化の型』のベネディクト、『サモアの思春期』のミード、『様式と文明』のクローバー、『言語―ことばの研究序説』のサピアなど、弟子たちの著作の翻訳にすでに親しんできた私たちに、そうした一連の人類学的知性の起源にあった大いなる泉の存在がいま初めて示されたのだ。この源泉には未知の可能性が秘められている、と訳者は詳細な解説のなかで示唆している。文化を、固有で静態的な「型(パターン)」に還元しようとしたベネディクト流の視点から、より動的で万華鏡的な文化概念へと進んでゆく可能性。人類という種の限界を見据えてその文化的可能性を引き出すアクチュアルな視点が、ボアズという源泉の中に秘められている。大村敬一訳。
渡辺公三氏(立命館大学教授)/東京新聞 2011.5.22朝刊
現代アメリカ人類学の父、フランツ・ボアズが1927年に出版した主著の待望の翻訳である。期待にたがわず、ポアズの鋭い観察と考察を、密度の濃い読書として追体験させてくれた。
ボアズはドイツに生まれ、物理学分野で北極海の研究をしたことがきっかけでイヌイットの人々に接し、人類学に転進した。アメリカで市民権を得て、コロンビア大教員として後進を育てながら反人種差別の論陣を張り、調査を通じてアメリカ先住民の文化の固有の価値を明らかにした。芸術論の古典ともいえる本書は、ボアズが生涯をかけて研究したカナダのブリティッシュ・コロンビア州太平洋岸に住む先住民の造形作品(トーテムポールもそのひとつ)を中心に、文字をもたずに技を伝承する人々の創作の秘密、すなわち世界への関わり方を突き止めようという試みである。
彼らの創造する美は手技の洗練の極致で生み出され作品に宿るリズムとシンメトリーにある。具象から抽象へ、あるいは抽象から具象へ、人間の創造力が「進化」したという十九世紀末の発想は実証に堪えないとボアズは主張する。圧巻は1897年の論文をもとに、動物の身体を切り開いて面上に配置する先住民たちが創案した「分割表現」を詳細に分析した第六章である。こうして表される獣たちに囲まれて生きるとはどういうことなのだろうか。
同じ97年には20世紀の人類学に大きな影響を与えた『クワキウトル・インディアンの社会組織と秘密結社』も刊行され、競って贈り物を与えあい相手の面子をつぶすことを競うポトラッチや、さまざまな動物たちの仮面が登場する冬の祭宴が詳細に記述された。
そこで描き出された先住民の多層的で錯綜した関係の網の目から固有の「造形の論理」を抽出し、他者の世界に到達しようとしたボアズの鋭い解析力は見事というほかはない。
池田光穂氏(大阪大学コミュニケーションデザイン・センター教授)/読書人 2011.7.15号
正直に言うと私には縁ある書である。1927年刊行になる本書の原著は1970年代中ごろ私淑した若い大学教師から奨められた本の一冊だからだ。入学したての私に対して彼は本書について興味深いコメントを残した。本書は、後に解釈人類学の祖と言われるようになるクリフォード・ギアツの37歳の野心的著作、農業の『インボリューション』(1963)を書くアイディアになったものだと。ギアツの書はジャワ中央東部の労働人□圧が文化と生態システムの内向きにむかうユニークな社会現象を分析した比類なき研究書、伝統農業システムの内旋つまり過剰な人口圧が限られた土地への更なる労働投下を生み農業生産性を限界まで引き上げる過程を描いたものだ。農業生態学と「未開芸術」がどうして繋がるのか? 理由はわからないが文化人類学とは「ものすごい想像力」を駆使するものだと私は瞬時に魅了されてしまった。
本書の著者フランツ・ボアズ(1858~1942)は北米派の文化人類学の創始者であり、数多くの弟子を育て偉大な父=パパ・フランツと呼ばれた。ボアズは一般には弟子たちに理論化を戒め民族と文化に関する詳細な記述(=民族誌)とその歴史的再構成や現地語による調査の重要性を強調した。他方で、当時の優生学的人種主義の台頭に対抗して彼は北米移民の形質人類学的身体計測調査などおこなって、人間集団の形質的変化の動態ゆえに人種差別には科学的根拠がないことを証明する「行動する人類学者」でもあった。
著者自身によって「芸術成長の動態的研究に関するひとつの研究」と記された本書は、しばしば誤解されるような未開芸術という特殊なジャンルの定立を目論んだものではなく、むしろ、人間の心的過程である美的表現の普遍性を信じ、芸術表現として顕れる現象は、地理と社会という環境要因の制約を受けながら歴史的な発展の産物であることを雄弁に語るものである。
本書は、世界の資料を参照にしつつとりわけ彼がもっとも精通した北米太平洋沿岸北部のクワキウトル(現在はクワクワカワクと表現される)先住民を中心として、北米の「プリミティブな人々」の素材を中心とした「アート=芸術」に関する美学的形相――言うまでもなく西洋美学を脱中心化する人間のより一般的普遍的な美的形式――に関する検討という前半部分(第一章~第五章)と、それらの理論的概念を用いて総合的に解説する後半部分の二つの部分に大別される。後半部分は、装飾、□頭を中心とした文学、音楽やダンスとの関連のなかで、極めて濃厚な記述と解説を、教養的知識習得を超えたあたかも〈固有の文化への接触体験〉するかのように楽しむことができる(第六章「北アメリカ北部太平洋沿岸の芸術」および第七章「プリミティブな言語芸術と音楽とダンス」)。
本書の価値は、訳者の大村敬一により徴に入り細を穿ちきわめて丁寧かつ正確に(=底本ドーヴァー版の対応ページが付されている)翻訳され、またかつ美的に配慮されて(=評判の悪かった同版からの図版ではなく初版から製版し直している)、詳細な日本語オリジナルの索引がつき、かつ二段組で百ページにも及ぶ訳者によるボアズの評伝・人類学的思考の特徴・現代思想への影響について詳細に論じられた解説が含まれており、この種の翻訳本ではおそらく世界で最高水準の出来栄えに仕上がっている。
ギアツは亡くなる五年前に冒頭で触れた自著の邦訳(NTT出版・2001)に際して序文を載せインボリューションすなわち(社会にすでに用意されている個別の芸術的要素が)内向きに洗練凝縮化するこの分析用語を「文化人類学の確立した概念」と改めて我々に解説してくれている。今年生誕百年を迎えた岡本太郎をはじめとして「現代芸術」の多くの芸術家の創造の源泉に「未開芸術」がもつ想像力が動員されたことは学術的に「常識」となっている。しかし、それはボアズが詳細に論じているように、現代に先行して「未開芸術」があったのではなく両方の活動とも同時代的(コンテンポラリー)に生じている現象であり、そこに見られる芸術的創造力の共通性や普遍性のほうに人は驚異すべきなのだ。この良質の文化人類学の遺産を芸術のみならず思想に関心のある読書人に是非とも勧めたい。さまざまなアイディアに満ちあふれた恐るべき書物であり、かつ大いに元気づけられる本なのである。
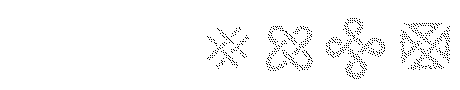 渡辺公三氏(立命館大学教授)/図書新聞 2011.9.3号
人が作りだした「もの」が人を魅了する力をもつ時、人はそれを美と呼び、「もの」にそのような力を宿す形を与える技をアートと呼ぶ。「アメリカ人類学の父」フランツ・ボアズ(1858~1942)は1927年に刊行された本書で、もっとも広い意味でのアートを「プリミティヴ」と呼んで、人間が美を生みだす力の源泉を見極めようとした。表題の「プリミティヴ」は、アーティストという職業としててはなく、人が素材に取り組み、素材からさまざまな可能性を引き出し、洗練された造形を生みだす、いわば常に真新しい経験としてのアートという主題の輪郭を確定するための形容詞であろう。同時代に支配的だった進化主義(西欧を人類進化の頂点とみなして非西欧を進化の遅れた段階にあるとみなす)と、それに同伴する人種差別の思想に真っ向から対決したボアズが、敢えて「プリミティヴ」という語を用いた意図はそのように理解できる。
プリミティブな美の表現に対するボアズの細やかな感受性に支えられた探求心が、現代人類学の根幹にかかわる大きな主題に導かれていたことは、巻頭の「緒言」から単刀直入に言明されている。すなわち、「現存するすべての人種とすべての文化形態で心的な過程は根本的に同じ」であり、しかも「すべての文化的現象を歴史上の出来事の結果として考え」なければならない。単一種である人類は、なぜこれほど多種多様な文化を表出しているのか。心的過程の普遍性対歴史過程の個性、その両者をどう総合して人類学を構築するか。新カント派的な響きが残るとしても、この問いは今も古びてはいない。その答えを、人類の造形活動に即して探求したのが本書なのだ。
原書の初版か刊行された1927年は、長命で旺盛な研究を持続したボアズの円熟期と、両大戦間期の現代人類学の、もっとも豊かな収穫期が交錯した稀有な時だった。人類学の基本書として広く流布したのは、黒い表紙に、一度見れば忘れがたい線画が配された1955年のリプリント版だろう。訳書では55年版を底本としつつ、図版はより繊細な初版から起こしているというのは読者にとって嬉しい配慮である。あのトーテムポールで知られたアメリカ北西海岸のクワキウトルやハイダの人々の、独特な造形の豊富な図版の生命は、何よりもシャープな輪郭線だからだ。
「序論」から始まり「芸術の形式的要素」「具象芸術」「象徴的意味」「様式」までの五つの章は、人類の造形表現を具象から抽象への進化と見るか、逆に抽象から具象への進化と見るかという西欧の同時代の美学の進化論的ドグマを反駁する考察を基調として、さまざまな素材を使った、籠編みの技や土器作り、彫刻など、手技の洗練こそ「プリミティヴアート]の必要条件であることを確認している。
「妙技」と訳された手技の洗練の頂点から、一歩離陸した地点に美が創出され享受される。そしてそのことは人類に普遍的な現象なのだ。手技の実現する製品は素材の制約を受けるいっぽう、素材の可能性を存分に抽きだして精緻化し、安定した「かたち」が類型と様式を生みだすとき、製品は作品となる。そこには美の源泉としてのシンメトリーとリズムが実現され知覚されるのである。
具象対抽象という図式の基礎には、「かたち」と意味、あるいは形の象徴的意味、形とその参照項の関係の問いが横たわっている。ボアズは北米インディアンの造形を中心に世界各地から収集された例に基づいて、形と意味は対応するはずたという先入観を打破する。たとえ形が何らかの対象を表す場合でも、「プリミティヴアート」では一つの視点からの像を描き出す(つまり物の裏側は見えない)遠近法だけにこだわるのではなく、対象の特徴を空間上に展開して並列する、野生のキュビズムとでも呼びたい画法をも創案する。それがユニークな「分割表現」とよばれる造形である。
結論的な五章までとは異なり第六章「北アメリカ北部太平洋沿岸の芸術」は、現在のカナダ、ブリティッシュ・コロンビア州のクワキウトル、ハイダ、トリンギット等と呼びならわされていた先住民族の造形の詳細な事例研究である。最も長いこの章は、訳者解説にあるとおり1895年に公刊された論文がもととなっている。したがってホアズが30代終わりの1897年に刊行した、今日読んでも興味尽きない『クワキウトル・インディアンの社会組織と秘密結社』という民族誌に巨細に描いた、先住民の世界の限りなく豊かな生活の細部から、造形の論理を抽出する作業が30年にわたって持続されたことが間接的にしめされてもいるのだ。「分割表現」の犀利な分析は、解説にあるように本書の白眉といえるだろう。
結論に先立つ第七章「プリミティヴな言語芸術と音楽とダンス」は第六章までの視覚的な造形の主題に対して、声と身体による時間芸術の造形をとりあげる。言葉、声すなわち詩と歌、そして身体表現としてのダンスは、踊ることのできる身体を獲得し、分節化した声の言語を獲得した人間にとって、もっとも普遍的でプリミティヴなアートなのだ。もし評者が、声と身体を「もの」と呼べば、強引の誹りをまぬかれないだろうが、これらは人が、人を魅了する力を宿す形をあたえることのできる、もっとも身近な生きた素材であることは確かである。ボアズの視点において、身体がいかに重要な位置をしめているかは、詳細な索引のなかで「身体部位」(ここには人間だけでなく動物のそれもふくまれる)の突出した比率が間接的に証言している。いっぽう言葉のアートは、ボアズがたびたび強調するように、その言葉を母語としない者にとっては、もっとも理解のむずかしい精妙なアートでもある。
視覚的芸術を優先した進化論的芸術論に対抗して、眼よりは手を重んじた籠編みの技や土器作り、彫刻など、身体が素材に働きかける手技から生まれる造形を起点に、視覚的なリズムやシンメトリーの美の検討をへたボアズの「プリミティヴアート」の探求は、こうしてアートのもっとも原初的で普遍的な源泉としての声と身体にたちもどることで閉じられている。そしてそれは、技の主体と対象がもっとも親密に交錯する、外部の観察者にとってもっとも接近しがたい源泉でもある。北西海岸インディアン、チヌークのダンスに魅了されたことがきっかけで人類学の世界に入り込んだというボアズは、こうして常に初心に回帰しつつアメリカ現代人類学の父となったとも考えられる。
息長い探求を総合した、錯綜した論述になりがちなボアズの論旨の展開の要点を的確に引用して整理し、伝記的事実と人類学史上の意義を簡潔に紹介した訳者の解説、そして詳細な索引は、本訳書をいっそう価値のあるものとしている。
渡辺公三氏(立命館大学教授)/図書新聞 2011.9.3号
人が作りだした「もの」が人を魅了する力をもつ時、人はそれを美と呼び、「もの」にそのような力を宿す形を与える技をアートと呼ぶ。「アメリカ人類学の父」フランツ・ボアズ(1858~1942)は1927年に刊行された本書で、もっとも広い意味でのアートを「プリミティヴ」と呼んで、人間が美を生みだす力の源泉を見極めようとした。表題の「プリミティヴ」は、アーティストという職業としててはなく、人が素材に取り組み、素材からさまざまな可能性を引き出し、洗練された造形を生みだす、いわば常に真新しい経験としてのアートという主題の輪郭を確定するための形容詞であろう。同時代に支配的だった進化主義(西欧を人類進化の頂点とみなして非西欧を進化の遅れた段階にあるとみなす)と、それに同伴する人種差別の思想に真っ向から対決したボアズが、敢えて「プリミティヴ」という語を用いた意図はそのように理解できる。
プリミティブな美の表現に対するボアズの細やかな感受性に支えられた探求心が、現代人類学の根幹にかかわる大きな主題に導かれていたことは、巻頭の「緒言」から単刀直入に言明されている。すなわち、「現存するすべての人種とすべての文化形態で心的な過程は根本的に同じ」であり、しかも「すべての文化的現象を歴史上の出来事の結果として考え」なければならない。単一種である人類は、なぜこれほど多種多様な文化を表出しているのか。心的過程の普遍性対歴史過程の個性、その両者をどう総合して人類学を構築するか。新カント派的な響きが残るとしても、この問いは今も古びてはいない。その答えを、人類の造形活動に即して探求したのが本書なのだ。
原書の初版か刊行された1927年は、長命で旺盛な研究を持続したボアズの円熟期と、両大戦間期の現代人類学の、もっとも豊かな収穫期が交錯した稀有な時だった。人類学の基本書として広く流布したのは、黒い表紙に、一度見れば忘れがたい線画が配された1955年のリプリント版だろう。訳書では55年版を底本としつつ、図版はより繊細な初版から起こしているというのは読者にとって嬉しい配慮である。あのトーテムポールで知られたアメリカ北西海岸のクワキウトルやハイダの人々の、独特な造形の豊富な図版の生命は、何よりもシャープな輪郭線だからだ。
「序論」から始まり「芸術の形式的要素」「具象芸術」「象徴的意味」「様式」までの五つの章は、人類の造形表現を具象から抽象への進化と見るか、逆に抽象から具象への進化と見るかという西欧の同時代の美学の進化論的ドグマを反駁する考察を基調として、さまざまな素材を使った、籠編みの技や土器作り、彫刻など、手技の洗練こそ「プリミティヴアート]の必要条件であることを確認している。
「妙技」と訳された手技の洗練の頂点から、一歩離陸した地点に美が創出され享受される。そしてそのことは人類に普遍的な現象なのだ。手技の実現する製品は素材の制約を受けるいっぽう、素材の可能性を存分に抽きだして精緻化し、安定した「かたち」が類型と様式を生みだすとき、製品は作品となる。そこには美の源泉としてのシンメトリーとリズムが実現され知覚されるのである。
具象対抽象という図式の基礎には、「かたち」と意味、あるいは形の象徴的意味、形とその参照項の関係の問いが横たわっている。ボアズは北米インディアンの造形を中心に世界各地から収集された例に基づいて、形と意味は対応するはずたという先入観を打破する。たとえ形が何らかの対象を表す場合でも、「プリミティヴアート」では一つの視点からの像を描き出す(つまり物の裏側は見えない)遠近法だけにこだわるのではなく、対象の特徴を空間上に展開して並列する、野生のキュビズムとでも呼びたい画法をも創案する。それがユニークな「分割表現」とよばれる造形である。
結論的な五章までとは異なり第六章「北アメリカ北部太平洋沿岸の芸術」は、現在のカナダ、ブリティッシュ・コロンビア州のクワキウトル、ハイダ、トリンギット等と呼びならわされていた先住民族の造形の詳細な事例研究である。最も長いこの章は、訳者解説にあるとおり1895年に公刊された論文がもととなっている。したがってホアズが30代終わりの1897年に刊行した、今日読んでも興味尽きない『クワキウトル・インディアンの社会組織と秘密結社』という民族誌に巨細に描いた、先住民の世界の限りなく豊かな生活の細部から、造形の論理を抽出する作業が30年にわたって持続されたことが間接的にしめされてもいるのだ。「分割表現」の犀利な分析は、解説にあるように本書の白眉といえるだろう。
結論に先立つ第七章「プリミティヴな言語芸術と音楽とダンス」は第六章までの視覚的な造形の主題に対して、声と身体による時間芸術の造形をとりあげる。言葉、声すなわち詩と歌、そして身体表現としてのダンスは、踊ることのできる身体を獲得し、分節化した声の言語を獲得した人間にとって、もっとも普遍的でプリミティヴなアートなのだ。もし評者が、声と身体を「もの」と呼べば、強引の誹りをまぬかれないだろうが、これらは人が、人を魅了する力を宿す形をあたえることのできる、もっとも身近な生きた素材であることは確かである。ボアズの視点において、身体がいかに重要な位置をしめているかは、詳細な索引のなかで「身体部位」(ここには人間だけでなく動物のそれもふくまれる)の突出した比率が間接的に証言している。いっぽう言葉のアートは、ボアズがたびたび強調するように、その言葉を母語としない者にとっては、もっとも理解のむずかしい精妙なアートでもある。
視覚的芸術を優先した進化論的芸術論に対抗して、眼よりは手を重んじた籠編みの技や土器作り、彫刻など、身体が素材に働きかける手技から生まれる造形を起点に、視覚的なリズムやシンメトリーの美の検討をへたボアズの「プリミティヴアート」の探求は、こうしてアートのもっとも原初的で普遍的な源泉としての声と身体にたちもどることで閉じられている。そしてそれは、技の主体と対象がもっとも親密に交錯する、外部の観察者にとってもっとも接近しがたい源泉でもある。北西海岸インディアン、チヌークのダンスに魅了されたことがきっかけで人類学の世界に入り込んだというボアズは、こうして常に初心に回帰しつつアメリカ現代人類学の父となったとも考えられる。
息長い探求を総合した、錯綜した論述になりがちなボアズの論旨の展開の要点を的確に引用して整理し、伝記的事実と人類学史上の意義を簡潔に紹介した訳者の解説、そして詳細な索引は、本訳書をいっそう価値のあるものとしている。
 Copyright(C)言叢社
Copyright(C)言叢社

