既 刊
表象交通論/西洋文化の起源へ/言語学
 ゲンゴキゴウケイトシュタイ
―イッパンブンカガクノタメノチュウシャクテキシカン
ゲンゴキゴウケイトシュタイ
―イッパンブンカガクノタメノチュウシャクテキシカン
●言語記号系と主体 ― 一般文化学のための註釈的止観
前野佳彦 マエノ ヨシヒコ【著】 ISBN: 4862090060 [A5判上製]528p 21cm (2006-03-31出版) 定価=本体3800円+税
§「言語記号学」の生成・拡張への徹底した批判・註釈を通して、「東洋」と「西洋」の表象文化、主体の形態と様相を対自化し、>「一般文化学」の覚醒・構築をめざす画期的試み。
【目次】
序 一般文化学の理念と〈現代〉の先験的構造
一般文化学の理念/一般文化学の今日的意義/先験的な現代性――定位の隠蔽と日常の露出/対自的覚醒の場の先験的構造/ヘーゲルの“西洋的”一般文化学のシステムの中での“東洋”の疎外/開化の外発性/同じ頃魯迅は/東北の田舎の狐はハイネの詩集を持ちツァイスの望遠鏡を注文した/一般文化学は定位の総体的な意味を対自化するために古典を参照する
第一章 基礎概念の査定――言語的記号系
/言語記号系の対自化/メタ言語論の視座/メタ・システム――言語論の資料選択の基準/メタ・言語論の資料群/メタ・システムによる古典時代の言語システム分析のためのモデル
第二章〈記号〉理念の誕生(ソシュール)
ヘーゲル的〈歴史〉からソシュール的〈記号〉への移行の必然性/ソシュールの『一般言語学講義』/記号学の理念/共時態と通時態/隠岐の旅館と京都の料亭(レヴィ=ストロース)/規範言語(langue)は言語活動(langage)ではない/規範言語(langue)は発話(parole)ではない/規範言語(langue)は書(écriture)ではない/能記(意味するものsignifiant)と所記(意味されるものsignifié)/記号の恣意性――能記は所記に恣意的に結合される/記号の恣意性――身体言語(礼式)/言語には差異しかない/恣意性の制限としての言語法則/言語は形態であって実体ではない
第三章〈記号〉理念の展開――意味論の捨象(チョムスキー)
統辞組織の変形生成システム――チョムスキーの普遍文法/表層構造と深層構造/変形生成文法――“痕跡理論”/“厳密に言語学的な変数”の分離(チョムスキー/レヴィ=ストロース)
第四章〈記号〉理念の展開――意味論の包含(ヤーコブソン/
バンヴェニスト/ロシア・フォルマリズム)
言語構造主義による〈記号〉理念の拡張(ヤーコブソン/バンヴェニスト)/記号の“二重性”と“統一性”(ヤーコブソン)/メタ・システム言語と対象言語(ヤーコブソン)/言語記号の連関としての諸制度の語彙(バンヴェニスト)/“買う”は“奴隷を買う”であった(バンヴェニスト)/ロシア・フォルマリズムによる〈記号論〉のエクリチュール的拡張/知覚の自動化に対抗する〈異化〉の手法(シクロフスキイ)
第五章〈記号〉理念の一元化(バフチン)
基礎概念査定の唯名的志向性/記号論と唯物弁証法の融合/あらゆる記号は社会的である(バフチン)/イデオロギーは記号である(バフチン)/記号と社会的コミュニケーション――イデオロギー現象としての言葉/意味は記号的関係の表現である(バフチン)/内的記号は意識の媒体である(バフチン)
第六章 エクリチュールと言語形而上学(デリダ/ベンヤミン)
エクリチュール派(言語形而上学)――ベンヤミン/デリダ/始源的な構造としての差異(デリダ)/すべてのものは存在する前に本である(デリダ)/“純粋な”フランス語/言語は事物の言語的本質を伝達する(ベンヤミン)/理念はあらかじめ与えられている(ベンヤミン)/アダムの言語――命名の根源性(ベンヤミン)/理念―本質相互間の埋め難い距離(ベンヤミン)/言語は記号ではない(ベンヤミン)
第七章 図像学(ワールブルク/パノフスキイ/ヴィント)
記号と図像――対自的指示作用の二重性/図像学――絵解きの伝統/造形芸術の意味(パノフスキイ)/デューラーの“メレンコリアⅠ”(ワールブルク)/ボッティチェリの“プリマヴェーラ”(ヴィント)/ファン・アイクの自然主義(ホイジンガ)/殷の礼制中に見られる二分現象(張光直)/図像学の一般文化学的視点からの査定 167
第八章 言語記号系の拡張――身体/服飾(賢治/ホイジンガ/九鬼)
言語的記号系の身体に沿った拡張/服飾は道具である(カーライル)/服飾は身体と意味の間に介在するdecorum(身だしなみ)の外的記号系である/外的統辞記号システムとしての身体言語/もういちどゴーシュとかっこう――decorumは? /身体言語の記号学的一覧表作成/民衆の想像力と聖者の服飾(ホイジンガ)/バロック的様式要素としてのかつら(ホイジンガ)/姿勢を軽く崩すことが「いき」の表現である(九鬼周造)/衣を解き槃礴して羸す――真の画工の身体言語と服飾(『荘子』)
第九章〈記号〉と〈主体〉
A.エクリチュールにおける〈差延〉現象と主体の〈中性化〉(デリダ/ヘーゲル/ベンヤミン)
記号系と主体/記号学とエクリチュール(ソシュール)/エクリチュールと“旧修辞学”(R・バルト)/陰謀家のおうむ返し――バロック的誇張法/差延から“本”へ
B.身体と〈自身〉(ニーチェ/定家)
記号系の外的統合の場としての身体/服飾/〈文体〉から〈身体〉へ/〈身体〉から〈自身〉へ
《結び》言語記号系における主体の隠蔽と顕現――註釈的止観から総体的止観へ
本文註
後記/参考文献/事項・概念索引/人物・書名索引
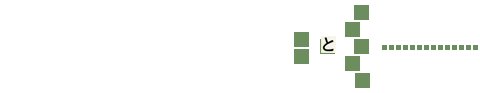
【著者紹介】 前野佳彦(1953年~) 福岡県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科修士課程修了ののち、シュトゥッドガルト大学及びロンドン大学付属ワールブルク研究所に留学。シュトゥッドガルト大学哲学部博士学位を取得、博士論文を出版(Der Begriff der Cultur bei Warburg, Nietzsche und Burckhardt, Hain Verlag bei Athenäum,1985.)。帰国後、在野にあって研究を持続し、東洋の、「われわれの」視点からヘーゲルの「精神現象学」を全て書き直すことをめざす。日本語の著作には、本書のほか『東洋的専制と疎外―民衆文化史のための制度批判』(文化史研究会、1987年)がある。
【書評】 「言語記号系」「主体」「一般文化学」「註釈的止観」という、表題の4つの言葉のやや見慣れない結合が、この著作の大きな企図と展望の深さを表している。 (渡辺公三/図書新聞 2006) 「言語記号系」とは20世紀初頭以来、〈現代〉の人文諸学をリードしてきたソシュール以後の言語学的記号論の潮流をさし、著者は独自の視点からその再構築を目指す。「主体」とは言語学的記号論が、論の成立の対価として不当にも抹消して省みなかったものであり、筆者によれば20世紀の思考を制約してきた〈意識〉や〈自己〉や〈現象〉とは一線を画しながら人間理解における鍵概念として回復されなければならない。主体生成の論理を組み込んだ言語記号系として構築される学こそ著者のいう「一般文化学」であり、その核心には、西欧的な学が排除した非・西欧の学を、中国そして日本の膨大な文献群に内在する「註釈」というかたちの人文学の論理として闡明することを目指す「註釈的止観」が構築されねばならない。この論理は知行一致の格律によって「生きられる」べきであるという著者の主張が「止観」という言葉にこめられていると理解される。表題の二語が主題を、副題の二語が方法を示していると理解してよいだろう。 東洋の知を統合しつつ記号と主体をとらえかえすという著者の企図は、〈現代〉の人文諸学を縦横に走査する多面的な解析力に主導されることで、論述にいくつかの明快で個性的な特徴を生みだしている。そのひとつは「序」と「結び」と9章からなる凝縮された本文と、字数では本文を越えるかも知れない豊かで多彩な註のバランスである。本文という骨格に註といういわば間組織的な豊かな肉付けがほどこされ、著者のバックグラウンドとしてのワールブルク研究、初期ニーチェ研究、フンボルト研究から、古代中国研究、魯迅、藤原定家、宮沢賢治にいたる、時に意表をつく鍛えられた読みの成果がふんだんに盛り込まれ、「註釈的止観」実践の例示となる。ドイツを中心とした西欧人文学への註釈は著者の独壇場の観があり、ニーチェ的な「楽しい学問」からの快心の笑いにも欠けていない。 簡にして勁い本文では、まず「記号論の発生の事情そのものが、〈歴史〉パラダイムの破産を宣告している」(「結び」の一節)という「先験的構造」の視点が提示される。20世紀の記号論は、キリスト教精神を相続し、精神の自己展開の運動を歴史に拡張したヘーゲルの自己=歴史の破産を確認し、歴史性を喪失した〈現代〉に直面した人文学が、この〈現代〉という狂気にも似た自己喪失という廃墟(著者は「記号の廃墟」と呼ぶ)の豊かな混沌に取り組むべく創出したものと位置づけられる。こうした〈現代〉はさまざまなかたちで生起した〈歴史〉の破産の、その都度経験されたひとつの「構造」だと著者は主張するのである。人類史にいくたびも現出しえた〈現代〉という「先験的構造」の直観をえて一般文化学の体系化を志すことになった契機を回顧する、「後記」に描かれた、研究所でのワールブルクのスクラップブック(まさに狂気を孕んだ記号の廃墟)をめぐるゴンブリッヒ教授との静謐な会話は、この著作のある切実な動機を鮮明に伝えて印象的である。 歴史とともに歴史の主体も廃棄し、さらには記号を創出する主体の概念も廃棄したソシュールによる言語記号概念の洗練過程の犀利な分析(第二章)は再読、三読に値する。この主体喪失に無自覚なままのチョムスキーと、意味論の再統合によってそれを克服する可能性を孕んだロシア記号論、ヤコブソンとバンヴェニストの言語学、きわめて明確に主体の再構築の道を示したとされるバフチン、ヘーゲルとは違った超越者を導入することで問題を見誤ったとされるベンヤミンとデリダ、記号から図像への展開をはかった図像学の主導者たち、これらの〈現代〉西欧人文学の峰々との渡り合いが各章を構成する。 こうした批判的註釈をとおして、著者のいう記号の根源にある力によって導出される「主体」を描出する主題が、いわば透かし模様のようにせり上がってくる。そして身体/服飾/decorum(もっとも広義の「作法」と理解できよう)の分析から、記号論的制度論、記号論的神話論への展望が素描される。註にもりこまれた豊かな知見とともに、ここでは断片的に言及されたレヴィ=ストロースの業績にも、予告された制度論、神話論の論考では踏み込んだ分析がほどこされることになろう。自覚的であれ自覚なしであれ著者のいう主体喪失の〈現代〉における人文学に携わっているすべての人にとって、主題の提示である本書を踏まえたうえで、予告された著作の刊行を括目して待つべきであろう。」
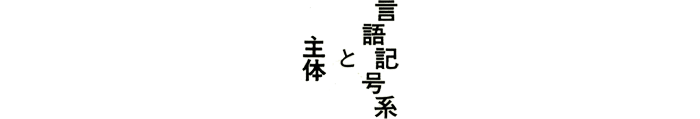 Copyright(C)言叢社
Copyright(C)言叢社
