既 刊
言語学/身体の思想/列島文化の起源へ/ 文化人類学・民族学・民俗学・歴史人類学
- ●主な目次
- ●著者紹介
- ●角田理論が示す問題群 角田理論が欧米言語学、欧米が築いてきた心的規範の拘束に対して、これをいかに相対化する ものかについての問題提起、この中で角田理論がいかに重要かについての概略を記しました。
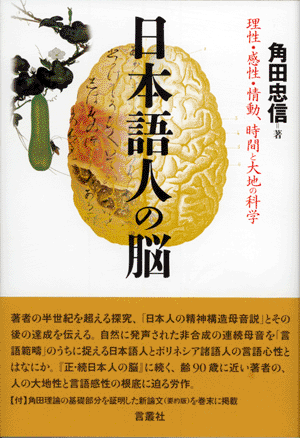 ニホンゴジンノノウ―リセイ・カンセイ・ジョウドウ、ジカンとダイチのカガク
ニホンゴジンノノウ―リセイ・カンセイ・ジョウドウ、ジカンとダイチのカガク
●日本語人の脳 ―理性・感性・情動、 時間と大地の科学
角田忠信 ツノダタダノブ【著】 ISBN: 978-4-86209-059-1 C3040 [四六判並製]333p 18.8cm (2016-04-15出版) 定価=本体2400円+税
§欧米言語学は、言語基盤にある母音の感性・情動性を理解してこなかった。日本語人は持続母音と虫の音を言語脳のある左半球で受容する。日本語人の心性、情動のありように迫る、齢90歳に近い著者による畢生の論文集。
●本書の著者・角田忠信博士の学説は、発表当時、多くの人たちの関心をひき、高い評価を得ながら、専門家たちからは批判あるいは無視され、葬り去られてきた。著者が提唱した「日本人の精神構造母音説」は、さまざまな誤解をふくんで流布したが、絞りこめば、たった一つの、著者による実証的事実から出発したものだ。 ●たった一つの実証的事実とは、欧米語を母語とする人では、持続母音(自然母音)は言語脳が位置する脳の左半球優位では受容されず、右半球優位で受容される(この実験をおこなったのは、著者ではなく米国の研究者である)。言いかえれば、欧米言語では、持続母音(自然母音)は「欧米言語の音声範疇」には入らない。子音―母音―子音といった音節としてまとまって、母音が「音声範疇」の中に入った時だけ、脳の左半球優位で受容される。 ●一方、日本語を母語とする日本語人では、持続母音(自然の母音)がそのまま「日本語の音声範疇」に入るため、即座に脳の左半球優位で受容される。日本語人以外で、持続母音を「言語の音声範疇」とする言語系は、著者が確認したところでは「ポリネシア諸語」以外には今のところ見当たらない、という実験実証に過ぎない。 また自然音、たとえば「虫の鳴き声」を、日本語人は「日本語の音声範疇」と同じ領域の地平で受けとめているが、欧米語人では「雑音」として右半球で聞き取ったり、鳴いていても聞き取れないことが多い。 ●著者が提唱した「ツノダテスト」については、厳密な追試の探究がなされずに毀誉褒貶を惹き起こしてきた。しかし、著者の探究は一貫した真理の探究だったことに疑いはない。ツノダテスト以外の方法による実証としては、菊池吉晃氏による脳波と脳磁図(MEG)を用いた実証だけだったが、本書では巻末に掲げたように、著者の子息・角田晃一氏(東京医療センター感覚器センター部長)ほかによって、作動時の脳内血流変化の測定にもとづく新たな実証がおこなわれ、国際的な専門誌Acta Oto-Laryngologica, 2016にその論文が掲載された。これにより、著者の日本語母音論は追試による基礎的な証明を得ることとなった。
【角田理論が示す問題群】 「日本人の母音の処理方式が世界の言語圏とは異質で、この差が日本人の精神構造と文化の差の基底にあるという説には、欧米諸国からも猛反発があり、ドイツ誌は日本人優越論を主張する超愛国主義者でナチスの再来とまで非難され、私の説は理解されずに非難を浴びせられた。」(本書「序にかえて」より) 著者の著作『日本人の脳―脳の働きと東西の文化』(1978年、大修館書店)、『続・日本人の脳―その特殊性と普遍性』(1985年、大修館書店)、『右脳と左脳―脳センサーでさぐる意識下の世界』(1992年、小学館ライブラリー)は、発表当時、多くの読者によって評価、注目されベストセラーとなった。ことに文学者からの評価は高く、安部公房氏の推薦により新潮社の「日本文学大賞」を受賞するという異例の評価まで起こった。ところが、著者が専門とする神経科学、耳鼻咽喉科学だけでなく、言語学、国語学の分野の専門家からは多くは無視され、一部からは批判された。また、欧米からの批判、非難にもさらされた。欧米からは、上記の引用のように主として「日本人優越論」のイデオロギーとして非難された。 しかし、著者が提示した問題群は、欧米文明が、その一元拘束的なシステムにより「去勢」あるいは「剪定」して造りあげた近代システムの力や大きさを確認しながら、この文化システムが排除した人間の深さと多様さに地位を与え、来るべき人類文明のかたちを構想するという大きな課題と深く結びついている。あくまで問題群の提示にすぎないが、関係するいくつかの問いをあげてみたい。 (1) 欧米言語学では、声帯気道から放出された音を、主として舌および唇の開閉の仕方により、言語範疇のうちに統御された音声を母音とする。この放出された音に含まれる主体表出の情動性は、定義からは排除されている(赤ちゃんが泣くのはなぜなのか。「胎児よ、胎児よ、なぜ躍る」のか。「無音」、「沈黙」も言葉ではないのか)。母音の言語範疇は各言語によって異なるから、母音の数も異なる。そして、母音がなければ音節は成り立たないことは理解されている。streetのように、strと子音が続いても、その後に母音がなければ音節は成り立たない。欧米語の基本は、子音+母音+子音の音節によって成り立つ。この場合、言語範疇としての拘束性はきわめて高く、日本語の発声でなされるような持続母音は、言語範疇から排除されて右脳で受容される。また、「虫の声」や「ため息」などの生理音も雑音として排除されて右脳に入るから、人によっては「虫の声」が聞こえないこともあるという。 しかし、日本語の母音は、母音だけでも意味を持ち、母音と子音との関わりでは欧米語のような厳密な拘束性を持たない。声帯気道(内臓器官)からの発声・発出がそのままに母音の言語範疇としてうけとめられている。日本語人は「虫の声」や「ため息」さえも、言語のように受けとめている。 (2) 「ツノダテスト」の実験にもとづく著者の「日本人の精神構造母音説」は、言語が左右の脳の神経構造にさえ影響を与えていることを示唆あるいは証明するものだった。角田理論への反発は、ここから生じた。欧米の脳神経科学が当時、到達していた常識でいえば、左脳は分析的、論理的な働きをもち、右脳が音楽その他、情動を含んだ全体的なものを受容する働きをもつとされた。ところが、著者は言語脳のある左脳が論理的なものばかりか、虫の声のような自然音、ため息のような生体内臓音、和楽器音、さらには情動的なものさえも受容しているのだと主張する(ただし、右脳に言語脳がある逆転型では全てが逆になる)。しかも、このような左右脳の特性をもつのは、調べたかぎりでは、日本語人とポリネシア語系の言語で育った人の脳だけだというのだ(あくまで調べた範囲でと限定すべきだが)。言語の差異が脳の機能や形態に影響を与えるなんて、その頃は容易には考えられなかった。欧米人の脳と日本人の脳がちがうなどということはありえない。実験そのものが、「超愛国主義者」のデマゴギーにすぎないと批判された。 (3) 現在は、この論争、攻撃から20年以上が経過した。今日の脳科学では、ツノダテスト以外でも、脳に対する非侵襲的な仕方で、活動する脳の状態を外部から観察できる手法がいくつも生み出された。そして、一連の研究の中で、欧米の文化が築き上げた「楽音組織の規則」が、脳の機能と形態さえ変えてしまっている事実が解明されるようになってきた。最も驚くべき事例をあげる。
(4) 「絶対音感」は、西洋の音楽文化が開発してきた「音階の基準」を、即座に了解・判断する脳の音階受容のありようを示す言葉だが、「絶対音感」に習熟している人の脳では、右脳の音受容の部位である側頭平面が「剪定」されて小さくなっているという(Julian Paul Keenan, Ven Thangaraj, Andrea R. Halpoern, and Gottfried Schlaug, Absolute and Planum Temporale, NeuroImage 14, 1402-1408, 2001)。西洋音楽の「音階規則」の習得は、右脳側頭平面の「剪定」という脳組織の機能と形態の改造さえおこなっていたのだ。 ほんらい、音の振動の高低は階段状ではなく、なだらかに生起している。しかし、西洋音楽の音階は、この音の流れに区切りを入れ、「離散的」な音階を徹底して脳に刻みこませなければならない。この訓練・習熟の結果、右脳側頭平面の「剪定」が引き起こされていたのだ。この事実が脳血流のイメージング技法によって確認された。 「音階」だけでなく、言語もまた「音素」「音節」といった音の抽出によって「離散的」な構造規則を造りだしている。それなら欧米語人は、「離散的」な構造規則の「拘束性」によって、日本語の自然音に近い持続母音に対しては、これを言語範疇から削除し、「剪定」していると考えてもなんらおかしくはない。 (5) 西欧言語学の基本は、「記号―記号対象」「シニファン―シニフィエ」という記号学の規則を踏まえて造られてきた。そこでは、「記号作用」を惹き起こす主体の感性、情動、意志といったものは、言語学の構造規則に登場しない。言い換えれば、「言語」は使用するための「道具」にすぎない。そして、この道具は、その規則性のシステムを認知する「理性」に属する。しかし、われわれが日本語から受け取っているのは、道具としての「日本語」なのだろうか。日本語の表現には、理性だけでなく、感性も情動さえもがこめられていると思ってはいないか。そして、この感性と情動の基盤には、人間の自然性があるだろう。 (6) ソシュールにはじまる西欧の構造言語学に対して、この国の国語を対象とする国語学には、かつて「時枝国語学」というすぐれた言語学があった。しかし、国語研究者は国語研究の内部でのみ研究を進め、西欧言語学はソシュール以後の業績に頼って研究を進めるのみで、一度として欧米言語学と国語学の差異がなぜ生ずるかの対話を怠ってきたのではないか。欧米で「詩」といえば、「踏韻」と「喩」の技法によって生まれるとされる。日本語で詩を創りだすのは「音数律」と「喩」とされてきた。「喩」については同じでも、なぜ言語の美は、欧米の「踏韻」にたいして、日本語では「音数律」なのか。こういう差異について、「なぜそうなのか」という問いを立て、答えようとしてきたことがあるだろうか。これらの問いは、角田理論が問うた問題群のうちに含まれていないだろうか。 (7) 中沢新一は、昨年の「京都こころ会議」の講演で次のように語っている。 「私はいま自分の喉の形や舌の位置や口の開き方などを微妙に調節しながら、こうして皆さんに話をしています。発声のすべての過程が無意識におこなわれます。喉から声を外に送り出す過程は、内臓の活動に直接つながり、それは身体の物質過程に直結しています。 言語はこうして発声される声の音の中から、ごく少数の要素だけを選んで音素として用います。選ばれた音素を組み合せて、言葉をしゃべるのです。これはすでに文化の領域に属する活動です。文化は自然のものから有用な要素だけを取り出して、システムをつくります。文化は自然から切り離され、自律性を持った活動をおこないます。そのために、身体や内臓活動につながる自然過程は、文化から分離されてしまいます。……」 「さっきの発話のケースで言えば、喉が発する言語音は内臓的な自然過程に直結しているのに、その事実を言語学の外に追いやって、自然音が言語に有用な音(音韻)に変形されたあとに始まる、文化的なコミュニケーションの世界のことばかりに、関心を集中させていく。……」(「『もの』と『こころ』の統一へ」『〈こころ〉はどこから来て、どこへ行くのか』[河合俊雄・中沢新一・広井良典・下條信輔・山際寿一著]岩波書店、2016年3月) この中沢新一氏の言葉の背景には、三木成夫氏の「生命形態論」があり、また、三木の「生命形態論」と本書の著者(角田忠信)の「母音論」を踏まえた吉本隆明氏の『母型論』、とりわけ「大洋論」の影響がうかがえるだろう。とはいえ、そこから展開する中沢の「同型論」「喩論」は、レヴィ=ストロースに学ぶところがもっとも大きかったろう。そして、ここに示された問題群は、現代のわれわれの生命のありようにとって、とても大切な課題を与えている。 本書は、著者の子息・角田晃一氏による追試論文が国際的な専門誌(Acta Oto-Laryngologica, 2016)に評価・掲載されたことをも踏まえて、角田理論が提起する問題群の大きさを改めて世に問いたいとの思いで、出版したものです。(言叢社編集者・島)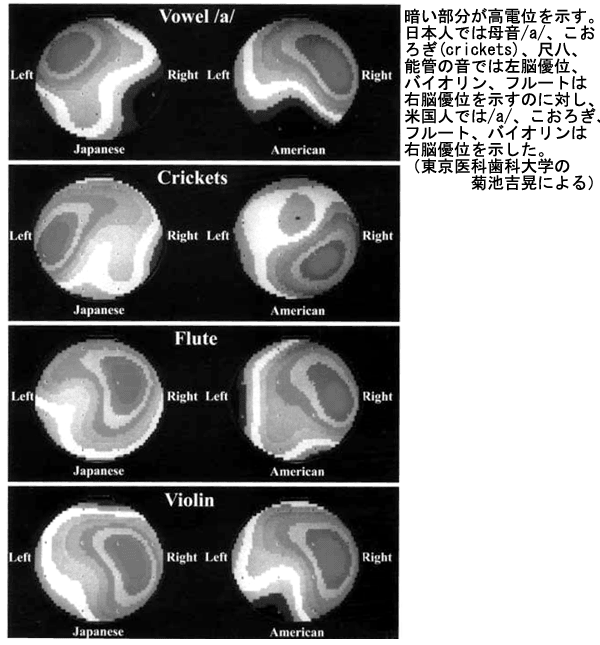
【主な目次】 序にかえて―私の研究の歩み 本書を読むにあたって 第一部 日本語人の特質―左右脳の非対称性と脳幹スイッチ機構 1.脳の感覚情報処理機構からみた日本人の特徴と今後の脳研究の方向 2.人の脳の非対称性と脳幹スイッチ機構の意義 3.ツノダテスト、新法の開発⑴―打叩する位置によるツノダテストの検討 4. ツノダテスト、新法の開発⑵―脳の機能差をめぐる最近の動向と脳の加温法について 5.左右脳と和洋音楽 第二部 日本語人と脳の情動性 1.ヒトの嗅覚系、情動脳、自律系の非対称性について 2.性機能の脳のラテラリティー 3.脳で行われる自他母音の自動識別について 4.自他識別機構の研究―「母の声」、「母の視線」の優位性 5.脳センサーから見出された新しいシステム 6.脳センサーの反応から推測される時代の変革 7.人脳センサーによる地殻歪みの評価と予期せぬ知見 8.人の脳の非対称性と脳幹センサーの意義―四〇・六〇系、十八日系 第三部 人の脳にある生物学的時間単位と脳センサー 1.人の脳にある正確な一・〇〇〇〇秒の時間単位 2.人脳に見出された生物学的基本時間単位一秒の意義 第四部 対話と反論 1.脳の中の小宇宙―驚くべき脳センサーの話(対話者 峰島旭雄氏) 2.不思議な日本人の脳と日本語の力―われわれの美意識はどこから生まれたか(対話者 林秀彦氏) 3.『日本人の脳』への誤解をとく―P・デール氏への反論 おわりに 【最新報告】Acta Oto-Laryngologica掲載論文の要約(角田晃一氏ほか) 角田忠信著作目録
【著者紹介】 角田忠信(1926~) 東京府中野区生まれ。1949年、東京歯科医専卒(東京医科歯科大学の前身、耳鼻咽喉科)。1951年に同大学助手、1957年に講師、同年に「鐙骨固着度の検出法」で東京医科歯科大学にて医学博士。1958~70年、国立聴力言語障害センター職能課長。1983年、東京医科歯科大学難治疾患研究所教授。1986年、『脳の発見』で日本文学大賞(学芸部門)受賞。1990年、東京医科歯科大学名誉教授。
