既 刊
●身体・歴史・人類学 Ⅰ アフリカのからだ ●身体・歴史・人類学 Ⅱ 西欧の眼 ●身体・歴史・人類学 Ⅲ 批判的人類学のために
表象交通論/身体の思想/現代思想/ 文化人類学・民族学・民俗学・歴史人類学/ 現代社会・制度
 ●身体・歴史・人類学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●身体・歴史・人類学 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
Ⅰ アフリカのからだ
渡辺公三 ワタナベコウゾウ【著】 ISBN: 9784862090294 [四六判上製]412p 19cm (2009-07-14発行) 定価=本体3200円+税
§個体を駆動させる力と多層の文化システムとの相関を問う。
王・首長の存在、文化システムへの支配権・霊威の「委託」は、同時にこれに拮抗する「個体」の文化の豊かさを失うものではなかった。 現代の一元的な社会・文化システムの駆動が、多層の文化システムを失わせ、個体の文化の力をいかに偏らせたかを照らし出す人類学の試み。
【目次】 Ⅰ=1.クバにおけるンシャーン(転生)―再生あるいは自己の中の他者 2.話すこと・食べること・黙すること―クバ文化における身体のフィギュール 3.穴と蟻塚―アフリカにおける大地=子宮のイメージ Ⅱ=4.布の始源―草ビロード(ザイール・クバ王国)の空間とリズム 5.布の造形と社会空間―クバ王国からのノート 6.王の隠された身体クバおよびレレにおける王権の形成と否定) Ⅲ=7.多産の王と不能の王―クバおよびレレにおける王権の形成と否定 8.クバ王権とショワ首長権―一王国(ザイール・クバ王国)内での比較の試み) Ⅵ=9.病いを宿すからだ―アフリカの伝統的病い観から 10.妖術告発裁判における「語り」の論理―アフリカの事例から 11.森と器―治療者はどのようにして治療者となるか(クバ王国の事例から)
【著者紹介】 渡辺 公三(1949年~) 東京生まれ。東京大学社会学研究科文化人類学専攻博士課程修了。国立音楽大学講師を経て、現在、立命館大学大学院先端総合学術研究科教授。 著書: 『身体・歴史・人類学1―アフリカのからだ』『身体・歴史・人類学2―西欧の眼』(2009年、言叢社)、『闘うレヴィ=ストロース』(2009年、平凡社新書)、 『司法的同一性の誕生―市民社会における個体識別と登録』 (2003年、言叢社)、『レヴィ=ストロース―構造』(1996年、講談社、2003年再刊)他。 訳書: 『食卓作法の起源』(『神話論理3』レヴィ=ストロース著、2007年、共訳、みすず書房)、『ホモ・ヒエラルキクス』(デュモン著、2001年、共訳、みすず書房)、 『個人主義論考』 (デュモン著、1993年、共訳、言叢社)、『国家に抗する社会』(クラストル著、1987年、水声社)他。
【書評】
擾乱をとどめるラフィア布とマルセル・モースの話し声
人間存在の西欧近代的なあり方とは別のあり方の探求
(昼間 賢/フランス文学・音楽評論)
「死者はしばしば、ある男を父として、あるいはある女を母として持ちたいがためにその子供として再生するという。言いかえれば、死者はその夫婦に何らかの美点を認めたからこそその子として再生することを望むのである」(引用は「クバにおけるンシャーン(転生)―再生あるいは自己の中の他者」『アフリカのからだ』より)
この度「身体・歴史・人類学」という総称のもとに『アフリカのからだ』と『西欧の眼』の二冊が刊行された。著者は渡辺公三氏。名著『レヴィ=ストロース 構造』(講談社)の、そして他に類書のない『司法的同一性の誕生』(言叢社)の著者として、またレヴィ=ストロースやルイ・デュモンの翻訳者として、フランス人類学とともに調査と思索を重ねてきた大家である。二冊とも、この二五年の間に発表された様々な文章から成っているが、読後感は、念入りに準備された書物を読み終えた充実感だ。理由の一つは、各部の始めに掲げられたイントロダクションが、それでわかりやすくなるのはもちろん、独特の距離感を感じさせる、不思議な魅力をたたえているからだろう。もう一つは、明確でいて含蓄の豊かな、渡辺氏の独特な文体にある。それは、淡々としたモノローグなのに、蒙昧な問いかけにも答えてくれる、開かれた知性の表現である。
第一巻『アフリカのからだ』は、中央アフリカのコンゴ民主共和国(旧ザイール)の内陸部にあるクバ王国で、六年がかりで行われた調査の集大成である。その目的は「人類学という分野のなかで、社会をアイデンティティー装置という視点で再考すること、身体を脅かす病いに人々はどう対処するのか知りたい、という二点」にあった。その過程で氏は、ラフィアヤシという植物の繊維で作られた民族衣装の重要性に気づき、しかしそれを単に美化するのではなく、「ある造形をめぐって〈社会〉から考えてゆく」試みに着手する。クバ王国の衣装は、日本でも時々展示されたり、民芸品として購入できたりするようなので、その種の関心から接してもいいだろう。氏は美術書『アフリカンデザイン クバ王国のアップリケと草ビロード』の共著者でもある。
本書の要点は、門外漢だから許されることとして提起するならば、人間存在の西欧近代的なあり方とは別のあり方の探求にあると思われる。「近代的個人」に対しては、すでにレヴィ=ストロースが「種としての個人」という見方を示しており、その重要性は、まさに氏のレヴィ=ストロース論で論じられたとおりだ。近代以降の、個別化された個人の集合体である社会は、たとえば「温暖化」のような、原因が無数にある問順に対応できない。「公共圏」も「ベーシック・インカム」も、最終的には、人間の生存に必要な、いわば中間地帯をどのように確保するのかという問題であり、なかでも切実なのが、いわゆる少子化問題だろう。今日の窮状は、本来は種の保存のために行われるべき生殖が個人の選択の問題になってしまった結果であると考えられるが、本書の「序文」がクバ王国に関する本論とは一見関係のなさそうな「母の生成 母子関係の自然誌のためのノート」という論考であることにも窺われるように、生殖、より正確には世代交代の問題は、本書全体に鳴り響く通奏低音のような役割を果たしている。男と女というたった一つの違いのために、かくも多様な関係が成立することは、人類学の教えのなかでも最も貴重な教えだろう。本書では、クバ族や近隣のショワ族の興味深い事例が報告されている。前者では、王は一夫多妻婚(庶民は変則的な一夫一妻婚)であり、それが衣装との関連で詳述される「王の隠された身体―クバにおける王権と衣装」は大変おもしろい。後者では、「ショワの首長は、その出自をたどればしばしば奴隷の子供だ、という」こと、またレレ族においては、支配する部族出身の女と支配される諸部族の男たちとの間に一妻多夫制が成り立っていて、その女は「村の妻」と呼ばれるなど、興味は尽きない。この地域の婚姻形態は、生産の権力も再生産の活力も男性中心に組み立てられた近代社会の側から見ると、非常に人間的な創意工夫の産物ではないか、そんな気がする。文化としてより高度なのは彼らのほうなのだ。本書の議論に戻ろう。「こうした一群の形象は、〈豊穣と多産〉すなわち〈性と生殖〉あるいは再生産という〈できごと〉の主題をめぐる、さまざまなそれだけの数の、この地域で独自におこなわれた思考実験とみることができる。それらの実験をいわば縦に貫いて、王という観念を極とした、ひらかれた社会空間の構造化という主題が展開される。性と再生産をめぐる観念の複合を王に集中し、中心をそなえ極性を帯びた社会空間を構成するか、王を再生産の回路から巧妙に分離し、異質な社会空間を生成し保持するか。多産の王と不能の王の形象がその縦軸の両極をなしている……」。人類学は、特にレヴィ=ストロースの構造人類学以来、諸関係の水平的な記述に専念する傾向があり、それに対して政治学的または歴史学的な批判がなされてきたわけだが、この見解は、長年の課題を克服する有力な手がかりであると思われる。
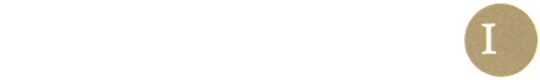 こうした卓見は、いまだ途上にある者にとっては感動的であれ、渡辺氏においては、俗界への報告義務を順守したまでであろう。氏のフィールドワーク(それがどれほど困難な状況下で続けられたのかは何も語られていない)には、もっと大きな射程がある。それに気づくのは、やはりラフィア布をめぐる考察の素晴らしさだ。氏のまなざしは、豪勢に着飾ったクバの王の頭上を見据えている。やがては消えゆく王の身体。権力は空白となり、相応の意味を帯びていた構造は、根本的な恣意性が明らかとなる。集団は危機にさらされる。そのとき、良いものも悪いものも何もかもが押し流されることのないように、一枚の布が、不穏な空気をときほぐす。クバの「草ビロード」は、そんな役割を担っているのだ。
「私達の幻想の中にある不可視の領域と〈この世界〉との目に見えない境界面を現実化するものとなりうる」のが、衣装の象徴的な機能なのである。クバの人々は、一生かけて、ビロードの経帷子を用意する。この世を離れる瞬間が人生の頂点ということ。なんと合理的で優雅な世界観なのだろう。
第二巻『西欧の眼』は、第一部の冒頭に記された「ザイールで、人類学調査という名目のもとでわたしは何を見ていなかったのか」という峻厳な自問とともに始まる。であればこそ、この眼は、見る側が見られる側でもある主客消滅の一点なのだろう。続く十四の文章は、第一巻とは対照的に一定の主題を持たないように見えるものの、最初と最後がマルセル・モース(一八七二~一九五〇)論であることに注目したい。一九二五年に刊行された『贈与論』の著者として、レヴィ=ストロースやバタイユなど様々な思想家や作家に影響を与えたことで知られる、知の巨人である。
なぜいまモースなのか? 本来不要な問いではあれ、あえて述べるならば、昨今の世界については、レヴィ=ストロース的な透明な視線よりも、モース的な、いわば直観的な総合力のほうが有効ではないか、そんな思いが広く共有されているのかもしれない。事実、近年はモース再評価の機運が高まっていて、デヴィッド・グレーバーが『贈与論』のモースをアナーキズムの側に引きつけてみたり、モースの弟子だった音楽学者アンドレ・シェフネルの仕事が注目されたり、日本では世界初となる全集の翻訳プロジェクトが共同作業で進められていたりする(渡辺氏もその一員として主導的な役割を果たされている)。意外なところでは、呼びかけという主題を介して、モースとサルトルが結ばれる。あるサルトル研究者は『贈与論』のモースの立場を「市場経済に対する批判的立場」(澤田直『〈呼びかけ〉の経験 サルトルのモラル論』平凡社)と見なしているが、そうした大胆な読み替えが、専門研究の枠を超えて、たとえば近年盛んな反グローバル化的アナーキズムの文脈に受け継がれてゆく。本書の言葉に従えば「モースの人類学的探求の根底には、多様なかたちの二分法を失効させ、知をあらたに再編するという意識的で強い意志があったように見える」のだ。
各論については、浅学非才にも理解できたものから列挙しよう。「ナショナリズム・マルチナショナル・マルチカルチュラリズム 多文化主義の歴史的文脈」では、模範的とされてきたカナダとオーストラリアの多文化主義、そしてケベック州の分離独立主義が、アフリカにおける多国籍企業と国家との結託といかに密接な関係にあったかが記されている。個々の文化表現しか知らないまま多文化主義を論じたことのある者なら、己の無知を恥ずかしく思うだろう。二冊を通じて唯一の未発表原稿である「パトリス・ルムンバ ひとりの〈開化民〉の生成と消失」は、最近の研究の成果を活用しながら、非業の死を遂げた政治家の生涯をたどり直している。サルトルのルムンバ論のていねいな再読に触発されながら、アメリカ黒人の歴史が、そしてフランス郊外の移民の現状が脳裏をよぎる。ここに提示された問題は未解決のままだ。また本書には、サーリンズ、デュモン、アンジュー等について、もともと翻訳書の解説や書評として発表された文章が収められている。言及されている本を読んでいないと真の理解は難しいが、数多くの書評を書いたモースの場合と同じように、渡辺氏においても、書評から得られたものが氏の思想の重要な部分を占めているように思われる。「歴史人類学の課題 ヒストリアとアナール学派のあいだに」や「アメリカ人類学の発生現場を検証する モーガンとインディアン〈土地問題〉へのメモ」は、専門研究者には必読の論考であろう。それから、第一巻でも(たとえば「病を宿すからだ アフリカの伝統的病い観から」において)展開されているように、氏の関心は「病い」から人間の心理全般に向かっている。構造が不変ならば、人間の心理には今も昔も共通の傾向が認められるのかもしれない。その点で「幻想と現実のはざまのインセスト・タブー フロイトからレヴィ=ストロースヘ」は興味深かった。「男たちが〈断念〉を共有することで、女性の交換が成立する。これは果たしてフロイトが太古のできごととして描いた兄弟集団による姉妹の断念、すなわちインセスト・タブーの生成と同じ事態を指し示しているのだろうか」という一節は実に刺激的である。この「断念」は、第一巻で描き出されたクバとその周辺の独特の婚姻形態と、関係づけられるのかどうか。研究の深化が期待される。
人類学とは、人間の事象に関する総合的な学問である。法学、社会学、心理学、文学など、他の分野が個別化する過程で見過ごしてしまったものを呼び覚ましてくれる。人類学は、人間の事象から慣習的な価値を剥ぎ取り、確固たる骨組みを提示する。そこに各種各人が共通する場が開かれるものの、それは西欧近代が目指した普遍とは別物だろう。むしろ新たな唯物論の実験場であるだろう。そして人類学が人文諸学の王座に即くとき、その力点は、成文化された社会における不文律の領野に置かれるにちがいない。たとえば贈与。贈る者は、贈るべき人の格を見定め、それにふさわしい贈り物を選び、それに想いを託す。それが通じたとき、贈られた人の格が定まるとともに贈った者の格も定まり、双方ともに、個人を超えた広がりの中で安らぎを見出す。贈与は人の為ならず。ここで想いと呼んだものは、モースの用語に置き換えれば「祈り」である。祈りが通じない社会、眼に見えないものが単にないとされてしまう社会では、革命を行うか、輪廻転生を願うしかない。せき止めた者は、そのまま朽ちてゆくだろう。『アフリカのからだ』と『西欧の眼』は、たとえばこんな風に、読めば読むほど深遠な世界に読む者を誘う。
こうした卓見は、いまだ途上にある者にとっては感動的であれ、渡辺氏においては、俗界への報告義務を順守したまでであろう。氏のフィールドワーク(それがどれほど困難な状況下で続けられたのかは何も語られていない)には、もっと大きな射程がある。それに気づくのは、やはりラフィア布をめぐる考察の素晴らしさだ。氏のまなざしは、豪勢に着飾ったクバの王の頭上を見据えている。やがては消えゆく王の身体。権力は空白となり、相応の意味を帯びていた構造は、根本的な恣意性が明らかとなる。集団は危機にさらされる。そのとき、良いものも悪いものも何もかもが押し流されることのないように、一枚の布が、不穏な空気をときほぐす。クバの「草ビロード」は、そんな役割を担っているのだ。
「私達の幻想の中にある不可視の領域と〈この世界〉との目に見えない境界面を現実化するものとなりうる」のが、衣装の象徴的な機能なのである。クバの人々は、一生かけて、ビロードの経帷子を用意する。この世を離れる瞬間が人生の頂点ということ。なんと合理的で優雅な世界観なのだろう。
第二巻『西欧の眼』は、第一部の冒頭に記された「ザイールで、人類学調査という名目のもとでわたしは何を見ていなかったのか」という峻厳な自問とともに始まる。であればこそ、この眼は、見る側が見られる側でもある主客消滅の一点なのだろう。続く十四の文章は、第一巻とは対照的に一定の主題を持たないように見えるものの、最初と最後がマルセル・モース(一八七二~一九五〇)論であることに注目したい。一九二五年に刊行された『贈与論』の著者として、レヴィ=ストロースやバタイユなど様々な思想家や作家に影響を与えたことで知られる、知の巨人である。
なぜいまモースなのか? 本来不要な問いではあれ、あえて述べるならば、昨今の世界については、レヴィ=ストロース的な透明な視線よりも、モース的な、いわば直観的な総合力のほうが有効ではないか、そんな思いが広く共有されているのかもしれない。事実、近年はモース再評価の機運が高まっていて、デヴィッド・グレーバーが『贈与論』のモースをアナーキズムの側に引きつけてみたり、モースの弟子だった音楽学者アンドレ・シェフネルの仕事が注目されたり、日本では世界初となる全集の翻訳プロジェクトが共同作業で進められていたりする(渡辺氏もその一員として主導的な役割を果たされている)。意外なところでは、呼びかけという主題を介して、モースとサルトルが結ばれる。あるサルトル研究者は『贈与論』のモースの立場を「市場経済に対する批判的立場」(澤田直『〈呼びかけ〉の経験 サルトルのモラル論』平凡社)と見なしているが、そうした大胆な読み替えが、専門研究の枠を超えて、たとえば近年盛んな反グローバル化的アナーキズムの文脈に受け継がれてゆく。本書の言葉に従えば「モースの人類学的探求の根底には、多様なかたちの二分法を失効させ、知をあらたに再編するという意識的で強い意志があったように見える」のだ。
各論については、浅学非才にも理解できたものから列挙しよう。「ナショナリズム・マルチナショナル・マルチカルチュラリズム 多文化主義の歴史的文脈」では、模範的とされてきたカナダとオーストラリアの多文化主義、そしてケベック州の分離独立主義が、アフリカにおける多国籍企業と国家との結託といかに密接な関係にあったかが記されている。個々の文化表現しか知らないまま多文化主義を論じたことのある者なら、己の無知を恥ずかしく思うだろう。二冊を通じて唯一の未発表原稿である「パトリス・ルムンバ ひとりの〈開化民〉の生成と消失」は、最近の研究の成果を活用しながら、非業の死を遂げた政治家の生涯をたどり直している。サルトルのルムンバ論のていねいな再読に触発されながら、アメリカ黒人の歴史が、そしてフランス郊外の移民の現状が脳裏をよぎる。ここに提示された問題は未解決のままだ。また本書には、サーリンズ、デュモン、アンジュー等について、もともと翻訳書の解説や書評として発表された文章が収められている。言及されている本を読んでいないと真の理解は難しいが、数多くの書評を書いたモースの場合と同じように、渡辺氏においても、書評から得られたものが氏の思想の重要な部分を占めているように思われる。「歴史人類学の課題 ヒストリアとアナール学派のあいだに」や「アメリカ人類学の発生現場を検証する モーガンとインディアン〈土地問題〉へのメモ」は、専門研究者には必読の論考であろう。それから、第一巻でも(たとえば「病を宿すからだ アフリカの伝統的病い観から」において)展開されているように、氏の関心は「病い」から人間の心理全般に向かっている。構造が不変ならば、人間の心理には今も昔も共通の傾向が認められるのかもしれない。その点で「幻想と現実のはざまのインセスト・タブー フロイトからレヴィ=ストロースヘ」は興味深かった。「男たちが〈断念〉を共有することで、女性の交換が成立する。これは果たしてフロイトが太古のできごととして描いた兄弟集団による姉妹の断念、すなわちインセスト・タブーの生成と同じ事態を指し示しているのだろうか」という一節は実に刺激的である。この「断念」は、第一巻で描き出されたクバとその周辺の独特の婚姻形態と、関係づけられるのかどうか。研究の深化が期待される。
人類学とは、人間の事象に関する総合的な学問である。法学、社会学、心理学、文学など、他の分野が個別化する過程で見過ごしてしまったものを呼び覚ましてくれる。人類学は、人間の事象から慣習的な価値を剥ぎ取り、確固たる骨組みを提示する。そこに各種各人が共通する場が開かれるものの、それは西欧近代が目指した普遍とは別物だろう。むしろ新たな唯物論の実験場であるだろう。そして人類学が人文諸学の王座に即くとき、その力点は、成文化された社会における不文律の領野に置かれるにちがいない。たとえば贈与。贈る者は、贈るべき人の格を見定め、それにふさわしい贈り物を選び、それに想いを託す。それが通じたとき、贈られた人の格が定まるとともに贈った者の格も定まり、双方ともに、個人を超えた広がりの中で安らぎを見出す。贈与は人の為ならず。ここで想いと呼んだものは、モースの用語に置き換えれば「祈り」である。祈りが通じない社会、眼に見えないものが単にないとされてしまう社会では、革命を行うか、輪廻転生を願うしかない。せき止めた者は、そのまま朽ちてゆくだろう。『アフリカのからだ』と『西欧の眼』は、たとえばこんな風に、読めば読むほど深遠な世界に読む者を誘う。

